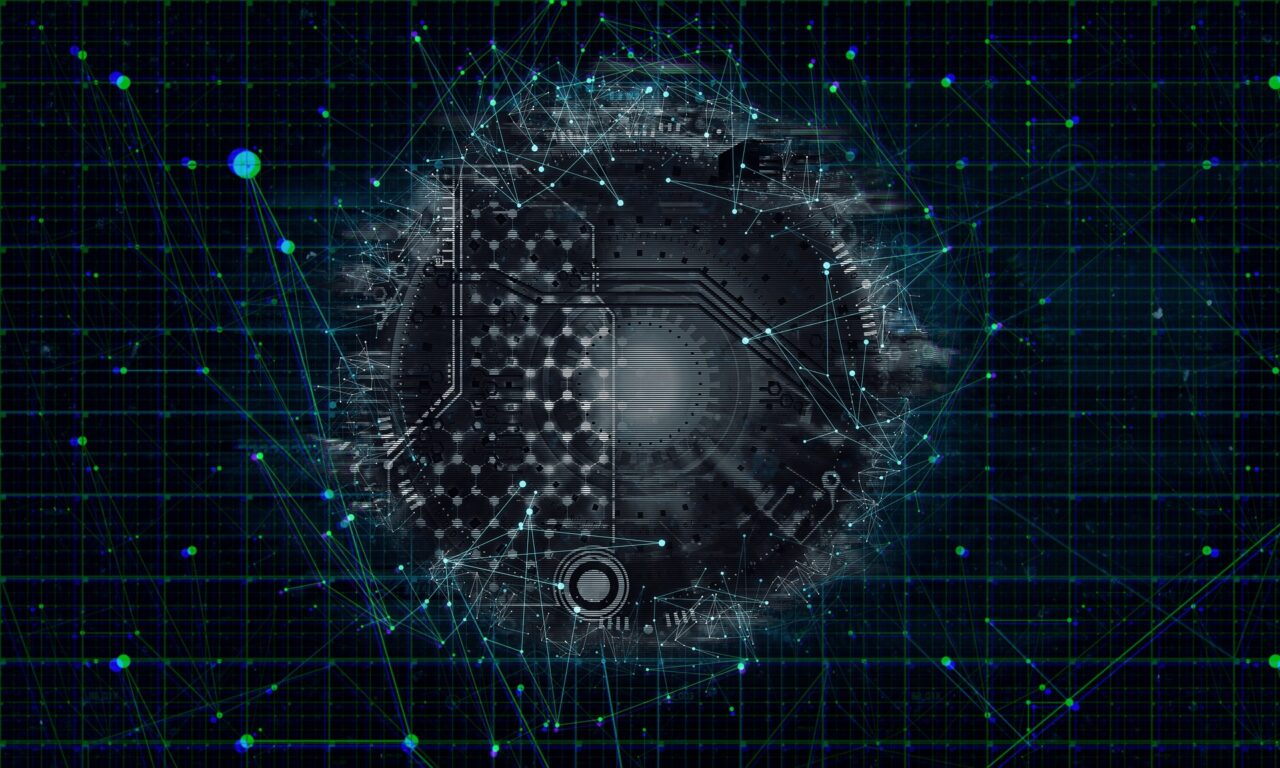車界の神様が目の前に降臨!
子供の頃、ロータス・エスプリがめちゃくちゃカッコイイと思った。
どうやらジウジアーロという人がデザインしたんだということがわかった。

それからカーデザイナーというのが存在するのだと意識するようになり、ジウジアーロさんの作品というのはどれも共通してカッコイイんだと気付いた。もちろん、ピニンファリーナやガンディーニなどがデザインした車も美しいんだけど、直線的で無駄がなく、ジウジアーロのデザインがすごく自分の中でしっくりくる気がしていました。
さらに、117クーペもスズキ・フロンテクーペも初代ゴルフもジウジアーロがデザインしていたんだと知って、自分の中の感覚が繋がる気がして、すごく納得した記憶があります。
そんなジウジアーロさんのことを好きな人は日本にも多いようです。また、ジウジアーロさんも日本や日本人のことを好きでいてくれているようです。
そんなお話をジウジアーロさんが来日し、2025年4月11日、オートモビルカウンシル会場でトークショーを行ってくれましたので、概要をかいつまんで残しておきます。
お父さんの勧めで絵だけでなく工業も学ぶ
ジウジアーロさんはお父さんは画家だったようで、画才は当初からお持ちだったようです。学生時代はやはり画家を目指し美術系の学校に通いますが、同時にお父さんの勧めで工業系の学校にも夜間通ったのだそうです。お父様は「画家なんて商売じゃ喰っていけねーぞ!」と思ったんでしょうか。芸術よりもうちょっと堅実な工業を学んでおいたほうがいいというアドバイスをしたのでしょう。それが後々、自動車はカッコだけじゃなく機能と生産性も必要なのだという考えに結びついたと思われます。
学生時代に、フィアットのデザイン部門に(おそらく、今で言うインターンのような形かな?)出入りするようになったようです。そこで働く、彼のオジサンに当たる人から卒業制作として「ちょっと車のデザイン描いてみない?」と言われます。提出した絵を見たオジサンが、こいつには才能があるぞ!と見抜きます。なんと、そのオジサンこそ、大ヒット作である初代フィアット500(ルパン三世が乗ってた2代目でなく、戦前のもの)の設計に関わったあのダンテ・ジアコーサさんだったんだそうです。才能ももちろんですが、周囲の環境にも恵まれてたんですね〜。
実はジウジアーロさん、17歳くらいまでは車には特に興味がなかったとのこと。なのに、自動車の絵を描く才能があったなんて、やはり天が与えし才能があったんですね。我々も神様に感謝したい気持ちです。
その才能を見抜いたオジサン、ダンテ・ジアコーサさんの推薦で、ジウジアーロさんはフィアットへ見習いのような形で入ります。そこで自身の天職だと気付き、自動車の世界で行きていこうと決めたのだそうです。
そこでの約4年間、エンジニアとして必要なことと、美意識あるフォルムを融合させなければと学びます。そして、友人の口利きで次に進んだのがカロッツェリア・ベルトーネです。そこでじゃあなにか描いてご覧よ、と言われて出来上がったのがアルファロメオ2600スプリントだそうです。
当時の多くの自動車は、まだフォルクスワーゲン・ビートルのようにフロントフェンダー前端にヘッドライトがついているのが常識だったわけです。そのヘッドライトをフェンダー呪縛からジウジアーロさんは切り離します。そしてそのために、フロントグリルの一部として収まるようなライト周りのデザインにしたのだと言います。
僕が子供の頃に描いていた車の絵はすでにフロントグリル内にヘッドライトを描いていましたが、このトレンドを作ったのもジウジアーロさんのようですね。
そしてさらに、ジュリアスプリントGTでは、ヘッドライトとウインカーを100mm以上離さなくてはいけないという北米の法規のため、四角いグリルの中にライトを一体化させ、ウインカーを外に出したとのことでした。
それを説明するため、会場でジウジアーロさんはスラスラと絵を描いて説明してくれました。
さて、そこから日本との繋がりが紹介されました。
日本から1960年のローマ・オリンピック出場を目指し、オートバイでイタリアに来ていた宮川秀之さん(さらりと言われましたがそれだけで本が1〜2冊書けそうですが)と出会います。宮川さんのお陰で日本を紹介され、また逆に日本サイドはカロッツェリアというデザイン工房の存在を知ることとなり、当時は知らなかった東洋工業(現マツダ)のお仕事を引き受けます。それでできたのが初代ルーチェのプロトタイプであるS8Pです。
S8Pはその後、東洋工業のデザイナー、モデラーのお陰でルーチェとルーチェロータリークーペとして、市販されるのでした。会場で偶然お会いしたマツダの前田育男さんも、「このS8Pが歴代マツダ車の中でも一番エレガントなんじゃないか、そのエレガントが後のマツダ車に受け継がれていると思う」と立ち話でですが語ってくれました。僕もそう思います。
さて、その後、次のクライアントとしていすゞを紹介され、初めて来日の機会を得てあの美しい117クーペが出来上がるわけです。その来日以来、「日本の皆さんには愛情深い対応、尊敬の念が心に残り、いつでも来日の際にはそれは変わらず、日本のことは第二の故郷のように感じています」とおっしゃったところで、会場からは大きな拍手が上がりました。
そうして、日本メーカーとの絆は強く広がることとなり、三菱、トヨタ、スバルなどと関係は続いていき、自身は自動車という世界中の街中で見かける製品をデザインすることができ、幸せだったとおっしゃいます。
彼の目線で見てきた日本メーカーの特長は、品質の高さだと言います。それは例え低価格の車両でも信頼性は素晴らしく、我々ヨーロッパの自動車業界も見習っているのだ、とのことです。
最後に驚くことをおっしゃいました。人の顔を構成するものは誰もが目と鼻と口で同じですが、ほんの少しの大きさや距離の違いなどで違った顔になっていることを例に出し、美しさというのは数字で出すことができるのだと巨匠は言いました。意外でした。僕自身、美しさは数字で表せないものだと感じていましたが、工業とデザインを学んで、世界中に美しい様々な製品を生み出してくれたマエストロは、多くの人の手に渡ることで成立するものだ。そのためには数字で表し、図面にして量産できるものでなければならないという意味にも通じると思いました。
もはや、自動車業界の神様のような存在を自分の目で見ることができて幸せでした。車が本当に深く好きになったし、車の色々なことが知りたいと思うきっかけの一つを彼が作ってくれた気がします。勝手ながら、僕の中の大切な感性を磨いてくれたお一人と思っています。まだまだお元気で、ご活躍をお祈りしております。
(文・写真:小林和久)