憧れの「限定解除」はいつの間にか「大型二輪」へと名称を変えていた!
思い起こせば40年以上前。通っていた高校には内緒で原付免許を取得し、それがきっかけで自動二輪中型限定免許も取りました。ヤマハMR50、スズキスワニー、ホンダCB50、カワサキZ250FT(あ、きれいに4メーカー揃ってた!)などを乗り継ぎましたが、大学生になるとバイクから遠ざかり、気づけば還暦の見える年齢——59歳の誕生日を迎えていました。
中型免許を取った当時、「いつかは限定解除を」と思っていましたが、いつの間にかその思いも忘れ、穏やかな中にも小さな波乱を乗り越えながら、それなりに人生を楽しんできました。幸い、国内外の試乗会やモーターショー、モータースポーツの取材も経験でき、東南アジアの密林に入っていくような冒険もしました。
ただ、残念ながら、同世代や少し若い知人が亡くなる場面に何度か直面し、「人生はいつか終わる」という事実を強く意識するようになりました。そんな時、ふと「何かやり残していないか?」と考えた末、「そうだ、限定解除に挑戦しよう」と思い立ったのです。
しかし、すでに免許制度は大きく変わっていました。「中型限定」と呼ばれていた免許は「普通二輪」に、「限定解除」と呼んでいた免許は「大型二輪」へと名称が変わっていたのです。何より驚いたのは、かつては試験場で一発合格するしかなかった大型免許が、教習所に通えば比較的誰でも取得できる時代になっていたことでした。
いや〜、我々の世代にとって、ナナハンに乗るには中免から限定解除するしかなく、そのためには試験場で限定解除試験を受け、合格しなければならなかったのです。そのため、「10回以上落ちた」「途中断念した」なんて経験談はざらに聞いてきました。
ちなみに僕は、昭和57(1982)年に取得した原付、昭和58(1983)年の自動二輪(中型限定)、昭和60(1985)年の普通免許一種、いずれも運転免許試験場での一発試験で取得しており、教習所には一度も通ったことがありませんでした。当時は、時間貸しの練習場で練習し、試験場に挑むというスタイルでした。
そんな僕が59歳にして、自動車学校に入学することに。ピカピカの一年生体験が始まります。
40年ぶりの免許取得、初めての教習所通い
どうせ通うなら、二輪メーカーが運営していて安心感があり、かつ通いやすい立地ということで「ホンダレインボーモータースクール和光」を選びました。
40年ぶりの免許取得、初めての教習所通い
というわけで、どうせなら二輪メーカーが運営する安心感と、比較的通いやすい場所にあることから「ホンダレインボーモータースクール和光」へ通うことにしました。
さて、昭和58年に取得した自動二輪(自動運転はしないくせに)免許時代、AT免許はありませんでした。クラッチ操作のないスクーターってのはカブに代表されるお仕事用を除けば、主にイタリアの女優ソフィア・ローレンが乗るラッタッタや、八千草薫さんまでもがCMしてたのにその後ヤンキー御用達となったパッソル/パッソーラなどの原チャリのものでしたが、今では大型二輪にもAT免許が存在します。
もちろん目指すは、MT(マニュアル・トランスミッション)の大型二輪免許です。
手続きを終え、教習スケジュールを組んでもらいます。土日はイベントがあるのでNG。そう伝えると、1日2〜3時限ずつのスケジュールが組まれ、約2週間で全課程を修了できる見込みとなりました。普通二輪免許を所持しているため、学科教習は免除されます。
以下は、2025年4月1日現在のホンダレインボーモータースクール和光の料金表です。
<大型二輪MT取得時、所有免許別の基本教習料金/ホンダレインボーモータースクール和光、2025年4月1日現在>
| 所持免許 | 学科 | 技能 | 教習料金合計 |
|---|---|---|---|
| なし (原付・小型特殊) |
26H | 36H | 298,100円 |
| 普通車 | 1H | 31H | 212,740円 |
| 普通二輪 | – | 12H | 110,110円 |
| AT普通二輪 | – | 16H | 131,230円 |
| 小型限定 普通二輪 |
– | 20H | 152,350円 |
| AT小型限定 普通二輪 |
– | 24H | 173,470円 |
| AT大型二輪 | – | 8H | 88,990円 |
| AT大型二輪 及び 普通二輪 (小型含む) |
– | 5H | 73,150円 |
すごく細かく別れていますね。これに大型AT取得希望だったらまた別の料金表となるわけです。二輪以外も大型、大型二種、中型免許制度の複雑さが垣間見えますね。僕は「普通二輪」所持者なので、11万110円ということになります。
どのタイミングでバイクに跨る? エンジンはいつ掛けたらいいの?
さて、いよいよ教習初日。まずは、正しいバイクの発進方法から教わります。
「ああ、そういえば40年前も、後方確認してから跨るとか、ミラーの視界が合っていても実際に触って確認したほうがいいとか、やってたなぁ」──そんなことを思い出しました。
初めて乗る大型二輪は、ホンダの教習車「NC750L」です。
ここで正しいバイクの発進方法をおさらいしておきましょう。
まず、ハンドルに両手を掛け、右側のフロントブレーキを握り、バイクを起こしてサイドスタンドを解除します。後方確認のうえバイクに跨り、右足をステップに乗せると同時にリヤブレーキを踏みます。このとき、右足を地面に着けてはいけません。基本的に、右足を着けてよいのは停止時にギアチェンジするときだけ。不用意に右足を着けると「ふらつき」と見なされることがあるそうです。
左右のミラーを合わせ、右手でキーを回してイグニッションをオンにします。左手でクラッチレバーを握り、右手でブレーキレバーを保持したままセルスタータースイッチを押してエンジンを始動。この間、右足は常にリヤブレーキを踏み続けておく必要があります。右手のブレーキも、右ミラーを調整したりキーを回すときなどを除いては、常に握っておきます。
まあ、このあたりは基本的な操作ではあるのですが、最初のうちは「あっ、ミラー合わせるの忘れてた」「前ブレーキを握らずにセル押しちゃった」など、つい凡ミスをしてしまいがちです。何度も繰り返して、「考えずとも自然にできる」ようになるしかなさそうです。
そういえば40年ほど前、免許を取ったときに「ここを試験場だと思わず、本物の道路だと思って運転したほうがいい。たとえば踏切なら、実際に電車が通るものとしてしっかり確認すると合格しやすいよ」とアドバイスされたのを思い出しました。今回も、その心構えで挑みます。
バイクでぐるりと周回した後は、いよいよ各種の課題にチャレンジです。坂道発進、スラローム、一本橋、急制動を体験していきます。
(以下の記述は、教習時の時系列とは必ずしも一致していません。また、すべてがスクールで教わった運転方法やコツに基づくものではなく、個人の感想が多分に含まれていることをご了承ください)
一本橋もスラロームもやり方がわからん!
教習でやるべきこと、教わったこと、できなかったこと、そして自分なりの解決方法をまとめてみます。
坂道発進や急制動は、日常的にも起こり得る場面の延長なので、特に苦手ではありません。ただ、スラロームや一本橋といった、いわば“曲乗り”的な運転は──そういえば40年ぶりで、まったくやっていませんでした。スラロームではパイロンに当たり、一本橋ではすぐにふらついて落ちてしまいます。
一本橋は、長さ15m・幅30cm・高さ5cmの細長い台の上を、大型二輪では10秒以上かけて通過することが目標です。しかし、とてもそんな時間を気にしていられる余裕はありません。何度も失敗を重ねていると、教官がフォームの問題点を具体的に指摘してくれたり、場合によっては教官運転の後ろに乗せてくれて実演してくれたりします。
一本橋のコツは、走り出したらエンジン回転を3000rpmくらいにキープしつつ、速度が落ちて「これは危ういか?」と思ったタイミングで、クラッチを僅かにつないで直進を保つことです。エンジン内部のフライホイールなどの回転体が高速で回っているほうが、地球ゴマのようなジャイロ効果で安定性に寄与してくれるのでは?とも思えますが、クラッチをつながないままエンジン回転だけを保って走るという経験がこれまでなく、苦手意識があります。ついアクセルを戻してしまうんですよね。
それから、少しスピードが出すぎた、あるいは安定してきたから減速したいというときは、リヤブレーキを使うのがコツ。前後の荷重変化によるバランス崩れが起きにくく、制動力もフロントに比べて弱いため、細かな調整がしやすいようです。
そして、自分が最もできていなかったと感じたのは、バランスを取るために体重移動で対応しようとしていたことです。たとえば、右に倒れそうになると無意識に体や頭を左に傾けようとしてしまう。しかし、それではバランスを保つことはできません。重要なのは、ステアリング操作によって進行方向を微調整し、重心をコントロールすることでした。また、シートの前寄りに座り、ステアリングにやや体重をかけてフロント荷重を意識することもポイントです。
そして何より大事なのは、「頭を動かさない」こと。前輪が一本橋に乗ったら、なるべく遠くの先をじっと見つめ、手元や橋自体を見ないようにするのが良いようです。
よく言われる「ニーグリップ」ですが、実際どのくらいの力で膝でタンクを挟めばよいのか、最初はまったくわかりませんでした。当然ながら目的はタンクを締め上げることではありませんし、それに気を取られていたら他の操作が疎かになってしまいます。そこで、自分なりに意識したのは、くるぶしを極力ステップの付け根に押し付け、足全体でバイクに密着させること。そうすることで、下半身がバイクと一体化したような安定感が得られると感じました。
一本橋は、教習では10秒以上を目標に練習しますが、卒検では10秒を切っても減点になるだけで、失格にはなりません。でも、脱輪すれば試験中止です。「これは落ちそうだ」と思ったら、思い切って速度を上げてでも渡り切るべきです。10秒を切っても、渡り切れれば減点で済みます。けれど、練習の段階で10秒以上の走行が安定してできないようであれば、本番で成功させるのはなかなか難しいだろう──というのが、後から実感したことでした。
スラロームは途中でアクセルを煽るんですって
次にスラロームですが、二輪でやった記憶がないんです。一般道でやるわけないし、40年前の中型限定二輪免許試験にあったのかな〜。無いはずは無い気がしますが、その場合でも、誰かから教わったのでなく独学でクリアしたんでしょうね。
スラロームは、4.5m間隔で置かれた5本のパイロンの間を左右交互に見ながら走り抜けるわけですが、ここでも知らなかったテクニックを教わりました。ギヤは2速、速度は16〜17km/hくらいに調整して侵入します。途中でクラッチは使いません。ライン取りは四輪と同じく手前側のパイロンのなるべく近くを通って、早め早めに向きを変え次のパイロンに備えます。練習時は、手前のパイロンに内側のステアリングエンドが当たるくらいに狙っていっても大丈夫です。
そしてこの向きを変えるタイミング、手前のパイロンをクリアしたな、という辺りで、空ぶかしのようにアクセルを一瞬煽ります。もちろん、クラッチは繋いだままです。駆動が一瞬かかることでバイクが起き上がり、向きを変えるきっかけにするのです。ちょうど、スキーで曲がっている途中、身体を伸ばして山側と谷側の体重移動を行うタイミングでストックを突くような感覚です。
このアクセルはスピードアップのためではありませんので、短時間で納めないと速度が上がってしまいます。一瞬チェーンを張るくらいの感覚でしょうか。しかし、単なる惰性だけで行ってしまうと、速度は落ちてしまい、目標タイムの7秒をクリアできません。速度が落ちない程度にアクセルを開けると言うことになります。
このスラロームのタイムも、一本橋同様に、卒検で7秒を超えたらアウト!というわけではありません。ですが、やはり練習ではコンスタントに7秒程度は出せるようになっているべきかと思います。
スラロームでも僕の場合、体重移動でパイロンをクリア、向きを変える、というイメージが強かったようです。「もっと肩の力を抜いて、ハンドルを切って曲がってください」とのアドバイスで、初めて7秒を切るくらいのタイムに到達しました。
坂道発進は、普通に二輪を運転できていれば、難しいことは特にありません。ただ気をつけるべきは、坂を登りきった頂上からは、十分に減速して15km/h以下くらいでゆっくり走ること。下り坂をゆっくり走れるかのチェックポイントでもあるのです。
また、急制動は 40km/hから晴れの日は11m、雨の日は14m以内で止まる必要があります。難しいのは止まることよりも、その指示速度でブレーキングポイントに入ることのほうがやや特殊な技術に思えます。スタートから1速、2速、3速とシフトアップして、3速のまま45km/h付近まで速度を上げてそれを維持し、ブレーキングポイントの少し手前でアクセルを戻してからブレーキをかけます。もちろん、クラッチは繋いだままです。停止直前にクラッチを握ることになりますが、そこでエンストしてもOKで、それだけでは減点にはなりません。エンジンが停まったら、落ち着いて再始動すればいいのです。ちなみにABSを効かせてしまうとロックしたと判断されるようです。
練習時には少し高めの速度からでも止まれるようにしておき、検定では狙えるだけ40km/hに近い速度で侵入すれば大丈夫かと思います。細かい点では、停止したときに右足を着いてはダメです。また、再発進時には後方確認をお忘れなく。
初体験の波状路ってなんだ?
さて、普通(旧中型)二輪には無かったのが波状路という謎の凸凹道。「でーこ〜ぼこー道や〜」と川の流れのようにで美空ひばりさんが歌ってたゆるやかな凸凹とはイメージが違います。
長さ9.5m、幅70cmの道路に、高さ5cmほどの四角い棒状の障害物が9個あり、そこをなるべくゆっくり走り抜けるわけです。5秒以上が目標で、エンスト、コースアウトは検定中止となってしまいます。実はこの9個の凸凹、よく見ると等間隔ではなく少しずつ間隔が違っているので、定速で走っても同じリズムでの衝撃にはなりません。
走り方はちょっと特殊です。まず立って走るのが基本です。やや前よりに軽く膝を曲げて、バイクのステップに立ち、膝で軽くタンクを挟み込むのが運転姿勢となります。そして、ローギヤでゆっくりと障害物に近寄り、アクセルは開けたまま、3000rpm位をキープします。そして障害物を乗り越える瞬間、ほんのわずか半クラッチを繋いで、わずかにトルクを伝えエンストしないようにしてあげます。繋ぎすぎると速度が上がってしまいます。この半クラを障害物ごとに9回行うイメージです。
僕はこの立って行う走り方の必然性から飲み込めず、この立たなければならない、クラッチを毎回繋がなければならないと、やるべきことを頭で考えて走ることとなり、なかなかスムーズに行きませんでした。確かに、オートバイをコントロールするのに、いろんなテクニックがあったほうがいいのはわかります。何を想定しているのかわからない凸凹道とそのクリアテクニックは、素直じゃない僕には、うまく飲み込めませんでした。けれど、それも何回か失敗を繰り返しながら、教官が教えてくださる注意点やテクニックを忘れずに織り込んでいくうちにうまく走れるようになりました。
コツは半クラッチの繋ぎ方です。クラッチレバーの繋がる位置よりも、もう少し手前でキープします。そして、つながる時は、ほんの一瞬繋ぐのですが、ちゃんと繋がっちゃダメです。ほんの僅か、半クラッチの半分の「4分の1クラッチ」くらいで、エンジンのトルクがちょっとだけ後輪に伝わるくらいを意識します。ちなみに、ここではクラッチを繋ぐことを「クラッチを開く」と表現していました。レバーを握っている手のひらを開くからでしょう。パワートレイン側の構造からすると「クラッチを開く」は「伝達を切る」ことなので逆ですね。色々あって面白いなぁと思いました。
コース走行練習にはコースを覚えること
さて、いろいろな課題の他に、コースをスムーズに走る訓練も必要です。指示速度までスピードを上げられるか、車線変更の安全確認のタイミング、右左折の仕方などとともに、コース内には鬼門とされることもある、S字とクランクがあります。
後で気づいたんですが、S字はある程度の速度でスムーズに走れるか、クランクはゆっくりと狭い道を正確に走れるかですので、それぞれスラロームと一本橋のテクニックの延長なのです。なので、S字の途中ではアクセルを一瞬開けて左コーナーから右コーナーに変わるきっかけを作ってあげればいいし、クランクは、一本橋が途中で折れているものだと思って、一本橋と同じアクセル、クラッチ操作、リヤブレーキ、体重移動でなくステアリング操作で走り抜けるのが正解かと思いました。
そのS字、クランクなどを含んだコース走行はAコース、Bコースがあり、決められたルートを覚える必要があります。最初から覚える必要はないんですが、ある程度時限が進んでいくと、教習開始時に「今日はAコースを走りましょう」とか「ABどちらでも好きな方から練習してくださいね」などと言われます。その段階で「あれAコースってどう走るんだっけ?」では練習にならず、結果として非常に時間がもったいないのです。なので、その前の教習が終わった時点で、次回はどういう走りをするのかを教官等に確認するのが良いかと、後になって思いました。
結果として、第1段階、第2段階ともにプラス1時間ずつ、計2時間の追加で卒業検定まで辿り着きました。1日に大体2〜3時間ずつ走れて、期間はおよそ2週間。意外に早かったように思えます。
卒検でまさかの「もう一回」
さて、すべての教習を終えた2日後、いよいよ卒業検定、いわゆる卒検です。
二輪免許の卒検は週4日ほど、通常の教習がある朝に行われています。
8時頃に到着し、ボードに書かれた受検番号と本日のコースが1コース(Aコースに規定を加えたコース)であることを確認します。2番でした。8時30分の開始まで、書類の提出、プロテクターやゼッケンを装着して待機します。受検なんて、何年ぶりでしょうか。懐かしい緊張感にすこしドキドキしてきます。
丁寧な説明を聞いて、質疑応答の後から、コースへと降りていきます。「次の人」までコース脇で待機するようになっています。
1番の人が走るのを遠目に見ています。気のせいか、なんか自分より上手い気がしますね。
1番が走り終え、いよいよ僕の番です。検定車両の横に立ったら、慌てずに後方確認からハンドルに手をかけ右ブレーキを握り、バイクを起こしてサイドスタンドを跳ね上げます。ちなみに僕が乗るSR400はキックスターターのみで、スタンドで立ってる状態でしかキックでエンジンを掛けられないのですぐに跨がりますが、そうしてはいけません。跨った時、右足をステップに乗せてブレーキを踏みます。決して右足を地面に着かないように気を付けます。ミラーを合わせますが、右ミラーを合わせるときとキーを捻るときだけ右ブレーキを離しますが、それ以外では握っています。イグニッションをオンにして、セルスタートスイッチオン。右ブレーキを離さないようにします。後方確認して右足を着いて、左足でギヤをローに入れます。
再び、後方確認して右ウインカーを出して、もう一度右後方確認して走り出します。走り出して合流の前にも後方確認します。卒検は同時に走行している車両もあるので、ホントに進路妨害しないように注意が必要です。そこで妨害してしまうと、たった1m走行で検定終了となってしまいかねません。
1コースは、大まかには外周からS字、また外周を走って内部に入り、信号機のある交差点、クランク、見通しの悪い交差点、波状路、外周から踏切に入って、教習時のAコースが終了。ここまでは自己採点では特に問題なく行けたと思っています。そして、そのまま課題コースに入ります。
課題コースはまず、坂道発進、坂道の下り坂からスラロームへ入ります。スラロームでは思ったよりスピードに乗せられず、7秒は切れなかったかな、と思いました。次に一番不安が残っていた一本橋ですが、10秒を目指すよりも完走を目指そう、と思い、やや速めかなと思いながらも渡り終えます。
さあ、次は最後の課題である急制動です。急制動は特に苦手意識もなかったので、ここまで止められず走れたから、これで最後までは行けたかな、と思っていました。
一本橋の終了地点から、ギヤをロー、セカンド、サードと速めにシフトアップし、46km/hくらいまで速度を上げ、ブレーキングポイントには44km/hくらいで進入、規定である11mの白線を超えることなう止めることができ、左足を着きました。とここで、検定員がこちらに向かってなにか叫んでいます。
「ガーン! なにかやらかしてたのか〜。終わった…(泣)」と思っていましたが、検定員曰く、「ブレーキポイントの手前で、後ろブレーキを掛けてましたので、外周を一周して、急制動だけもう一回やってください」とのこと。危ういところで検定中止ではなかった! 無意識にブレーキをかける手前で右足に力が入ってブレーキペダルをわずかに押していたんですね。気を取り直して、ここで検定員に、もう一度どこを通ってどのように再度急制動に戻ればいいかを確認しました。安全確認やウインカーをしっかり注意してコースへ戻り、再度急制動へ入ります。
今度はリヤブレーキを踏むことなくきちんと規定の距離内で制動ができたようです。
そうしてバイクをコースから左ウインカーを上げ、スタート地点まで進めます。左ウインカーを上げたまま、左足を着いてから、着地する足を右に変えてギヤをニュートラルに、エンジンを停止し、後方確認の後、バイクを降りて、サイドスタンドを降ろし、バイクを斜めに立てかけたら、ステアリングを左に切って、しっかりと固定されているのを確認したら終了です。
終わった時点ではまだ合否はわかりませんが、検定員に「スラロームも一本橋も時間が規定に達してませんでした。もう少し安全確認はわかりやすく、大きく首を振ったほうがいいですよ」と、まるで次は頑張ってね、というアドバイスのようにおっしゃいます。合格発表は、およそ2時間後の10時くらいになります。
いよいよ、本館ロビーのモニターにて、合格発表の時間となりました。
数字を追っていくと、2番の数字がありました! 一発合格でした!!
いやー、嬉しいもんですね。久々にこういった純粋な、人間のプリミティブな嬉しさを思い出した気がします。ちなみにこの日の大型2輪受検者は全員合格していました。
その後、今後の手続きやいろんな注意事項、初心者(そう言えば40年ぶりの初心者になったんですよね)に適用される免許、交通ルールなどを教えていただきます。
ちなみに、二輪免許を取得後1年間は2人乗りができなくなっています。我々の頃にはバイクの免許を取ったらすぐにでも彼女を後ろに乗せて…と妄想したものです(実行ではなく妄想です)。ただし、「2人乗りのバイクを運転できるのは、小型限定を含む普通二輪免許もしくは大型二輪免許を取得してから1年経過、または通算で1年以上経過している運転手のみ」とされています。中型限定2輪免許を取得してからは、遥か昔に1年は経過しているので、僕の場合は2人乗りOKとなります。
また、高速道路での2人乗りは昔はできなかったもんですが、主に大型バイクを販売する海外メーカーのお国の外圧によるものが大きいと言われていますが、2005年4月1日から、2人乗りが解禁されています。けれど、それも条件付きで、運転者の年齢が20歳以上で、二輪免許取得から3年が経過していることとなっています。こちらも、二輪免許を取得してから通算3年が適用となり僕は大丈夫です。誰か乗りますか?
お昼までには卒業証明書を受け取ることができたので、その足で東京都の府中運転免許試験場へと向かいました。バイクなら駐輪場は設置されています。
必要書類を用意(写真が必要です)して、手数料支払いのため、証紙を買います。この、手数料を支払うためにわざわざ切手みたいに印刷された証紙を買うというデジタル石器時代みたいな仕組みは証紙故に笑止千万だが、その手数料は4,200円(受験料1,850円、免許証交付料2,350円)となっています。受験料?(表記は受検料にあらず) なんだそれ、おいおい、試験は受けないよ、だってそのために試験免除となる学校を出てきたんだし、普通免許持ってるから学科試験も必要ないでしょ! とまったく持って納得いかないんだけど、ここでゴネても仕方がない。運転免許取得なんて一生のうちに何度もあるわけでないので、文句言う人も少ないのでしょう。けど、どこかで訴えたいですね。
それはともかく、書類作成、お約束の視力検査、免許証用の写真撮影を経て、旧免許と書類提出し、30分ほど待たされて免許受け取りの控えをもらいました。免許受取には1時間程度かかりそうなので、試験場内の食堂でカツカレーをいただきました。THE役場の食堂といった見た目に反して、味はまあまあでしたよ。まあ、カレーがまずかったら相当厳しいですけどね。
お昼を食べ終え、14時頃には新しい免許を受け取れました。
振り返ってみて、やはり、運転に関することは基本を知っているのが大事だと感じました。そんなことができなくたって運転できるでしょ、という部分もあるかも知れませんが、知らないよりは知っていた方が良いし、できないよりはできたほうがいいに決まってます。特に、運転はどんな危険に遭遇するか予想できないし、その時パニックになる可能性ある。だったら、基本を知っているのはある意味必要なこととも言えます。日本の面倒な免許制度も、ある程度必要だよな、と感じます。特に最近の「外免切替」問題も取り沙汰される中、そう感じました。
5月13日に教習を開始し、7日間で1日2〜3時限、追加2時限を含む14時限の教習を受け、5月27日に教習終了。5月29日に卒検、そのまま免許証交付となりました。思い起こせばわずか2週間の出来事でしたが、それなりに充実していました。教習開始直後の頃は、家に変えるとぐったりで、相当体力を消耗しているんだなと思いました。それにしても、この歳になったからこそ、なにか目標があるのっていいですね。次は電気工事士免許を目指したいと思います。
最後に今回掛かった費用をまとめます。
| 教習基本料金 | 110,110円 |
| 追加料金 | 10,560円 |
| 免許証発行手数料(運転免許試験場) | 4,200円 |
(小林和久)




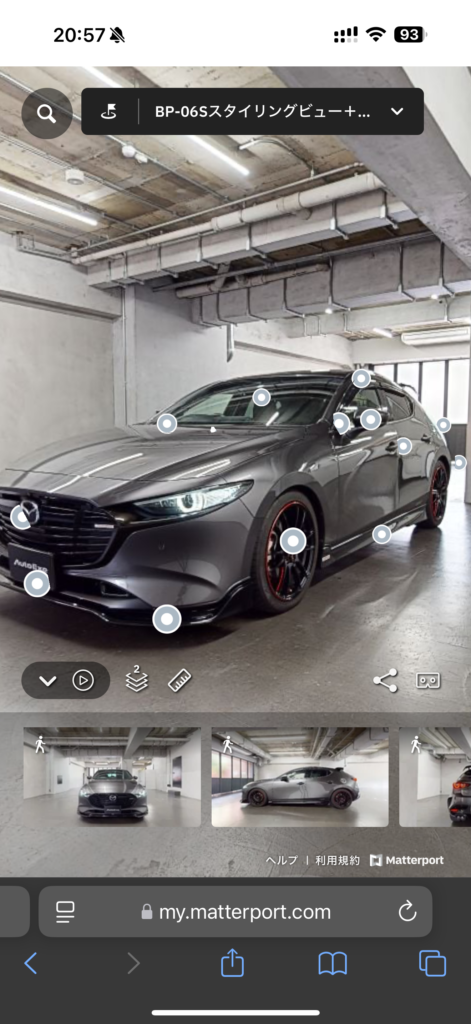
コメント